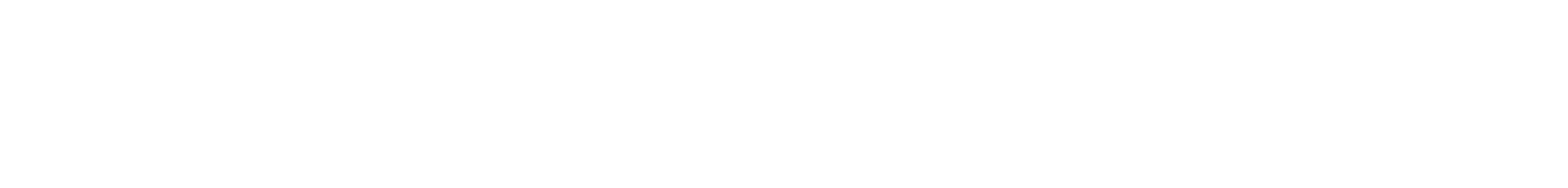忘れられた卯月の意味 〜旧暦に宿る日本人の感性〜

忘れられた「卯月」の本当の意味 〜太陰暦と日本の季節感〜
こんにちは、NORIです。
今回は、旧暦4月「卯月(うづき)」について、日本人がいつしか忘れてしまった本当の意味と、かつて私たちが使っていた太陰暦の季節感にふれてみたいと思います。
「卯月」は「卯の花」が咲く季節
旧暦4月は「卯月」と書きます。読みは「うづき」。この「卯」という字、十二支の「卯(う)」では?と連想される方もいるかもしれませんが、実はここでは「卯の花(うのはな)」が由来と言われています。
卯の花とは、別名「空木(うつぎ)」と呼ばれる植物で、ちょうど旧暦の4月(今の暦では5月中旬ごろ)に白く可憐な花を咲かせます。真っ白な小さな花が枝いっぱいに咲き、まるで春の幕引きを告げるかのように、静かに野山を彩るのです。
昔の人々は、この卯の花の咲く時期に季節の変わり目を感じ、田植えの準備を始めていました。自然と共に生きる感覚が、暦の名前にも息づいていたのですね。
太陰暦が教える、もうひとつの日本の四季
現在の私たちが使っているのは「新暦」、つまり太陽の動きを基準にしたグレゴリオ暦ですが、明治5年までは日本でも太陰太陽暦、いわゆる「旧暦」が使われていました。
太陰暦は月の満ち欠けを基準にした暦です。
月は約29.5日で満ち欠けを一周するので、1ヶ月は29日か30日。
12ヶ月では354日になり、太陽の暦よりも11日ほど短くなります。
そのズレを調整するために、2〜3年に一度「閏月(うるうづき)」を挿入していました。

この太陰太陽暦の素晴らしいところは、月のリズムに寄り添いながら、季節感もきちんと保っていた点です。たとえば、旧暦の4月は現在の5月中旬〜6月中旬にあたることが多く、「花冷え」の終わり、「田植え」の始まりといった季節の移ろいがそのまま感じられました。
暦と暮らしが結びついていた時代
「卯月」に限らず、旧暦の月の名前にはそれぞれに意味があります。
たとえば、如月(2月)は「衣更着(きさらぎ)」、弥生(3月)は「草木がいよいよ生い茂る」など、自然と共に暮らす日本人の感性が豊かに表れています。
現代ではカレンダーの数字だけを見て、季節を感じることが少なくなってしまいましたが、旧暦の世界に目を向けることで、私たちの祖先がいかに自然と調和して暮らしていたかを改めて知ることができます。
卯の花の咲くころに
現代の4月といえば、桜が散り、新緑が萌えはじめる季節。けれど、旧暦の「卯月」はそれより少し後、まさに卯の花が咲き、カエルの声が響き始める初夏のころでした。

白い卯の花が静かに咲く田園風景に思いをはせながら、「卯月」という言葉の奥にある本来の意味を、ぜひ感じていただけたら嬉しいです。

このように、暦には時代を超えて伝わる日本人の感性が宿っています。
忘れかけた季節のことばを、もう一度取り戻してみませんか?